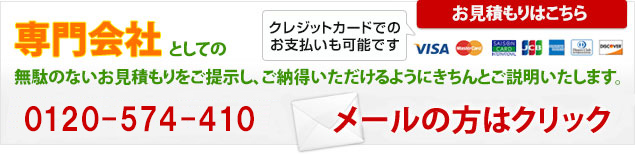駆除研究所 本日の現場ブログ
2015-03-27 花の後。
今日は、今週もギリギリセーフ!の事務の黒田ですorz
三月も末になり、弊社ご自慢の桜も次々と蕾が綻んでおります(^-^)
毎年見事に咲いてくれるのは、偏に葉桜の際に現場の皆がマメに消毒して、病害虫を寄せ付けない環境保持に努めてくれるおかげです(^人^)アリガトー
ええ、決して毛虫が降ってくるとお局事務員が消毒しろ!ヽ(`皿´)ノとヒステリーをおこしているわけではありません。念のため。
スクスクと育った桜は豪華に枝を広げ、樹高も高く、二階にある事務所の窓から素で花見が可能という眼福な環境です。
しかしながら、桜の豪華さを演出するこの樹高は一般家庭においてはクセモノで、個人規模の消毒機材では上まで薬剤を吹き付けるのが難しい条件となります。
また、垣根代わりに好まれる椿も、これからの時期はチャドクガをはじめとした病害虫の、格好の餌場となります。
桜や椿の花の後に付く害虫は、文字通り爆発的な勢いで増殖して、葉を食い散らかしていきます(;゚Д゚)
こうなると専門業者の機材でなければ、駆除は難しい状況になります(>_<)
一般家庭の樹木消毒も承っております。
晩春の庭木の害虫でお困りの際は、是非日東防疫にご相談下さい!
2015-03-24 点検時の定番の…
カマドウマ(竈馬)はバッタ目・カマドウマ科に分類される昆虫の一種で俗称で「便所コオロギ、オカマコオロギ」などとも呼ばれています。
キリギリスやコオロギ、ウマオイに似るが、成虫でも翅をもたず専ら長い後脚で跳躍する。その跳躍力は非常に強く、飼育器の壁などに自ら激突死してしまうほどである。背中の形や長い横顔などが跳ねる馬の姿を連想させ、古い日本家屋では竈の周辺などによく見られたことからこの名前が付いた。俗称として「便所コオロギ」などとも呼ばれる事もある。日本列島及び朝鮮半島の一部に分布するが、地域によっては体の色や交尾器の特徴などが微妙に変化しているため、いくつかの亜種に区別されています。
カマドウマという和名は、厳密には北海道から九州の地域と韓国に分布する原名亜種(複数ある亜種のうち最初に学名が付けられた亜種のこと)のみを指し、他の亜種には別の和名が付いている。しかしカマドウマ科の昆虫は互いに似たものが多く、日本産のカマドウマ科だけでも3亜科70種以上が知られ、専門家以外には正確な同定は難しい。したがって、明確な種別の認識なしにこれらカマドウマ科の昆虫を一まとめにカマドウマと言うこともある。この場合は「カマドウマ類」の意か、別種を混同しているかのどちらかである。
◎特徴
体長はオスで18.5-21.5mm、メスで12.0-23.0mmほど。メスは腹部後端に長い産卵管があり、この産卵管を含めると21.5-33.0mmほどになる。他のカマドウマ科の種と同様に、成虫でも翅をもたない。体はやや側扁し(左右に平たく)、横から見ると背中全体が高いアーチを描いた体型をしてる。背面から側面にかけては栗色で、腹面や脚の付け根、脛節などは淡色とる。各部には多少の濃淡はあるが、目立つ斑紋はない。幼虫も小型である以外は成虫とほぼ同様の姿をしているが、胸部が光沢に乏しいことや、第1-第3ふ節の下面に多数の剛毛があることなどで成虫と区別できる。
顔は前から見ると下方に細まった卵型で、口付近には1対の長い小顎鬚(こあごひげ)がある。体長の3倍以上ある触角で、暗所でも体の周囲全体を探れる。3対ある脚のうち後脚は特別に発達して跳躍に適した形になっており、腿節は体長とほぼ同じ長さがあり、脛節は体長よりも長い。
◎生態
主に身を隠せる閉所や狭所、暗所、あるいは湿度の高い場所などを好むため、木のウロ、根の間、洞穴などに生息し、しばしば人家その他の建物内にも入る。また時には海岸の岩の割れ目に生息することもある。古墳の石室内にも群生し、しばしば見学者を驚かせる。夜行性のため日中はこれらの隠蔽的な空所にいるが、夜間は広い場所を歩き回って餌を探す。夜に森林内を歩けば、この仲間がよく活動しているのを見ることができる(特に夏季)。また後述の通り樹液にも集まる為、カブトムシ等の採集の為設置したトラップに大量に集まるという事も珍しくない。
極めて広範な雑食性。野生下ではおもに小昆虫やその死骸、腐果、樹液、落ち葉などを食べている。飼育下ではおおよそ人間が口にする物なら何でも食べる。動物質、植物質、生き餌、死に餌を問わない。野外でも共食いがしばしば発生しているという。
繁殖は不規則で、常に卵、虫、様々な齢の幼虫が同時期に見られる
天敵はヤモリ、トカゲモドキ(南西諸島のみ)、ネズミ、カエル、各種鳥類、寄生蜂、カマキリ、アシダカグモ等である。
近似種との区別
カマドウマ科にはよく似たものが多いため正確な同定はかなり難しく、単なる絵合わせによって正しく同定をすることは不可能で、脚の棘や交尾器の形態などの詳細で正確な観察に基づいて同定しなければならず、それほど簡単ではない。特に幼虫の場合は専門家でない限り正確な同定はほぼ不可能と考えてよい。ある程度昆虫に詳しい者が行った過去の記録にもクラズミウマ などとの混同も少なくないという。
ただし家屋や納屋などに見られるカマドウマ科のうち、胴体や脚に濃淡の斑紋が明らかなものは少なくともカマドウマではなく、多くはクラズミウマかマダラカマドウマである。また一つの地域に生息する種は限られるので、産地や環境からある程度の種に絞り込むことも可能である。
2015-03-23 気温も高くなりだして・・・・
どうも黒木です
寒さもなくなりだして会社の前の桜も蕾も出だした三月末
四月半ばには桜も満開になりそうです
さて陽気な時期になりつつありますが虫たちも動き出す時期になります
毛虫が出たり幼虫が出たり増えてき、そのような人が見て不快に思う虫を不快害虫といい
ゴキブリ等衛生的に問題が出てくる虫を衛生害虫といいます
不快に思う虫に一つ五月ごろに出だす羽蟻
家の中で夜電気や昼間窓の周りに出てきて羽を残していく
それはもしかしたらシロアリの可能性が・・
シロアリじゃなくとも他の可能性があるので調査してみては?
2015-03-22 コウモリ ムカデ シロアリ 急増
おはようございます。Q太郎です。
先週から、グーンと暖かくなり日暮れも
だんだん遅くなってる気がします。
害虫 害獣が、キャンプ オープン戦を経て
シーズン開幕しました。
ガリガリ カサカサ ドスン 音(耳)
糞 尿 などの匂い(鼻)
ゴキブリ ネズミ ムカデ 毛虫(目)
害虫 害獣たちは、人の五感のうちの
三感を 特に 刺激してきます。
やはり、家で 快適に過ごせるのは
いいですよね。
朝の静かな ひととき
夜のゆっくり過ごすとき ガサガサ
いらないですね。
先日、東京でネズミ協議会に行ってきました。 今から先 ネズミとの大きな戦いがあります。面白い話聞けました!
今週は、天草で イタチの工事!
来週は、南区で大型物件の工事です。
広島営業所からの応援もお願いしてます。
ヤバイ ヤバイ 頭整理しましょ。
今週も、全力で行きます。

ハツカネズミが かじった あとです!

スカイツリー やっぱ!
東京 やね!
2015-03-20 環境整備。
今日は、事務の黒田@今日のブログは滑り込みセーフ!ですorz
卒入学シーズン最高潮の時期ですが、自分も先日魔法学校@大阪に受験しに行ってきました(嘘)
施設最大の目玉なだけあって、映画のセットそのままのような外構や建物は、歩くだけでも楽しい場所でした(*^-^*)
ですが、雰囲気を盛り上げる木立を見るにつけ、ああ、これからムカデや樹木害虫、夏になればハチの巣とか、環境整備が大変そう…という職業目線も存在しましたが(^-^;)
日に日に春めいてくる今日この頃、暖かい日差しにつられて、寒さで鳴りを潜めていた虫たちも、活動を始めます。
椿科の庭木にはチャドクガが、床下の換気網の奥にはミツバチが、日当たりが悪く湿気の溜まりやすい庭木の陰にはムカデが、そろそろ湧き出てくる時期でもあります(>_<)
気候の良いこの時期は、寒さに負けて疎かになっていた庭の環境整備を行って、来る夏の害虫を少しでも減らすのに最適な時期になります。
しかし、樹木の消毒や家の外周の摘要場所全体に、不快害虫予防の粒剤を散布するのは、専用の器材を持ち合わせていなければ、なかなか大変な仕事になります。
一般家庭のお庭の消毒も承っております。
環境整備をしても出てきた害虫でお困りの際は、是非日東防疫にご相談下さい!
2015-03-19 初めまして
初めまして、ニュータイプ佐藤です!(アムロじゃないです)
まだ、やっと入社して3ケ月になろうとしてます!
今から少しずつ暖かくなり、僕の好きなラーメン屋などの飲食店には、ガサガサと忍び寄って来る、黒と茶色のゴキブリが増えて来ますので、要注意です!
別府大分以外の九州内も駆除を行っていますので、日東防疫(株)と佐藤をよろしくお願いします!
PS・桜も咲き始めた季節ですので、冬眠から覚めた害虫・害獣に、動物・虫の産卵時期にもなってますので、要注意です!
2015-03-17 ムカデ?ではない…
どうも火曜日担当の中島です。
今週も先週に引き続き不快害虫について書かせてもらいます。
今回はヤスデです。
ヤスデ(馬陸)とは、多足亜門ヤスデ網に属する節足動物の総称で、細く短い多数の歩脚がある。
ムカデと似ていますが、生殖口の位置や発生の様式、体節あたりの歩脚の数など様々な点で異なるっています。
ムカデが肉食性であるのに対し、ヤスデは腐植食性で毒のある顎を持っていません。
体は数十個の節に分かれていて、足は前の3節には1節に1対ずつ、それより後ろの節は1節に2対ずつあります。
そのため、倍脚類とも言われます。
また、頭には1対の小さい触角があり、目は種類により(分類とはあまり関連無く)有無や数がまちまちなようです。
ほとんどのものは、固い外骨格を持ち、細長い体をしている。
腹面はやや平らだが、背面は大きく盛り上がって断面がほぼ円形になるフトヤスデのようなものから、扁平なヒラタヤスデまで様々います。
フサヤスデ類は他のヤスデほど細長くはなく、体が軟らかくて背面や尾部に剛毛の束を持つため、一見カツオブシムシの幼虫のように見える。
日本最大種はヤエヤママルヤスデで7cmほどになる。世界最大種はアフリカオオヤスデやタンザニアオオヤスデといったアフリカ産の大型種で最大30cmにもなるものがいるようです。
土壌の有機物や枯葉とそこにつく真菌類を主に食べていて、飼育下などでは意外に肉類も食べるそうです。
体表の毒腺から液体や気体の刺激物を分泌する種が多く、刺激を受けると体を丸めるものが多い。
通常は渦巻状にまとまって円盤となるが、球形になるタマヤスデ等もいます。
一般にはヤスデは害虫と見なされていますが、冤罪的な要素も多く、典型的な不快害虫です。
見た目が不快なことや、踏むと異臭を発すること、寒冷地の森林で周期的に大量発生するキシャヤスデなどの群れが鉄道の線路上に這い出して列車の車輪で踏み潰されると、その体液により列車がスリップすることなどが理由に挙げられています。
臭液の毒性は強く、狩猟用の矢毒として用いられた等という記録もあるようです。
また、「味噌汁に1個体が紛れ込んだら、鍋全部が食べられなくなる」などと言われる程で、密封すると自らの臭液で死んでしまう場合が多い。
その臭液は主に危険を感じた際に敵への威嚇として体外へ放出されることが多く、外敵に襲われた際は、ムカデと異なり積極的に顎で咬むことは無く、身体を丸めて自己防衛をします。
住宅やその周辺で発生するヤスデは一部の種のみで、多くのヤスデは森林で生活しています。
ほとんどの種は広意の土壌に生息して分解者の役割を担っており、森林中の落葉を食べ、糞は栄養分に富むため樹木の成長に影響を与えているとされ、
土壌形成上一定の役割を果たしているものと考えられており、食性と生態から自然界の分解者という要素が強い。
ほとんどの種は経済上直接に利用されることはなく、ペット(広義)として熱帯産のタマヤスデ類の大型種の一部が、メガボールなどと称していたり、フトヤスデ等が市販されることがあるようです。
不快害虫の忌避剤や農薬に防除効果を謳われるものがあります。
ある種益虫でもありますが、やはり見た目の不快さにはかなわないようですね。
ではまた来週お会いしましょう。
WordPress for Android から投稿
2015-03-16 シロアリ・・・・・種類について
どうも黒木です
今回は前回の続きでシロアリの種類についてです
種類は大きく分けると二種類
その中で代表的なのがヤマトシロアリとイエシロアリです
ヤマトは湿気を好み湿気があるところ特に床下部分によく見られ湿気があるところを食い荒らします
対してイエシロは湿気関係なくどこでも食い荒らしていきます
そのため家全体に発生します
駆除するときも全体を調査させてもらいますがイエの場合下回りだけしか被害がなくても上の方に逃げる可能性があるので家全体を消毒させてもらいます
駆除の方法として被害がある場所はもちろんのこと木部全体に穴を空けて(穿孔)いき薬剤を注入します
こうすることで色んな場所に潜んでいるシロアリに薬剤をかけることが出来駆除することが出来ます
予防の時も同様に穴を空けていきますが間隔は広く薬剤を木部に染み込ませて入らないようにするのが目的です
2015-03-13 寒の戻りも。
おはようございます、事務の黒田です。
今週初め、寒の戻りも戻りすぎ!な降雪が、あっという間に積雪となり、道が真っ白に雪化粧をしました。
しかし交通量も然程多くない道のアチコチで、何故か道の片側や一部の雪が、不自然に融けている珍百景…でも何でもなく、おんせん県おんせん市という環境らしく、道の下に温泉の配管が通っていて、地熱で雪が融けただけの話でした(^-^;)
ヌクヌクの温泉は助かりますが、同時に冬でも高温多湿な環境は、白蟻が好む環境でもあります(>_<)
この白蟻の駆除・予防は、夏しか行えない!と何故か誤解されている方が多いのですが、防蟻工事は通年して施工が可能です。
また、昔のような強烈な薬剤臭などもありません。
おんせん県のみならず、家の立地環境によっては五年に一度の白蟻予防が、家屋を長持ちさせます。
昨年夏、あるいはそれ以前の夏に、白蟻の群飛を見た事が…というお心当たりがありましたら、業者が比較的時間に余裕のある冬場、一度調査見積りを行う事をお勧めしております。
白蟻の駆除・既設物件の防蟻も承っております。
白蟻でお悩みの際は、是非日東防疫にご相談下さい!
2015-03-12 クモ駆除
おはようございます。Q太郎です。
3月も半ばに なります。
連日の イタチ工事で カラダが 痛い!
筋肉痛になっています。
昨日は、門司 ! 今日 明日 福岡!
明後日 宮崎! と 今週は 予定は、
ヤバイかな! イタチ ネズミ
動きが すごいです。
先日 施設調査に行って来ましたが!
クモ ムカデ ユスリカ 毛虫〔 チャドクガ〕
いろいろな 困ったが 出てきます。
部分を 見るのでなく
全体を見る 何も やらないと 結果は
無し!
あかりに集まる ユスリカなどのコバエを、捕食する為にクモは ライト周辺に、巣を 作ります。クモは、益虫ですが、 施設の外観を損ないます。
なかなか 厄介な 敵ですが 年間計画に
基づき 実際にやって見て 結果が出ます。
やはり 何事も やらないと
ダメですね。
今日も、安全第一! 行って来ます。

クモの巣 結構 ありますね!